「世界と人口」誌 2000.1 ずいひつ
ミエさん
文・絵:池内紀 氏
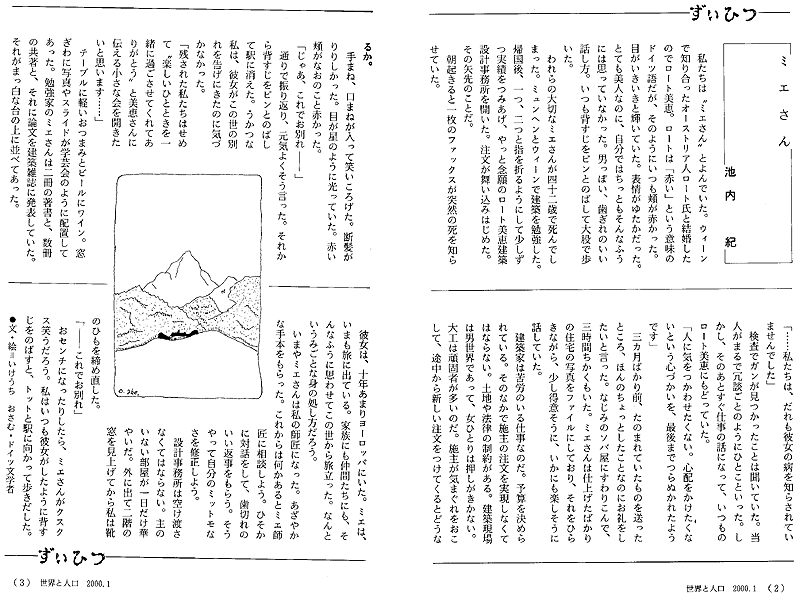
「世界と人口」誌 2000.1 ずいひつ
ミエさん
文・絵:池内紀 氏
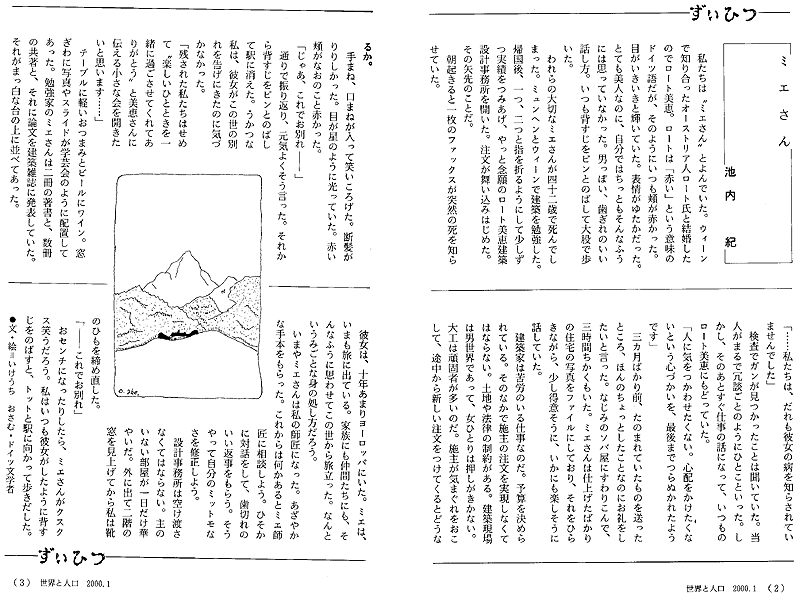
私たちは“ミエさん”とよんでいた。ウィーンで知り合ったオーストリア人ロート氏と結婚したのでロート美恵。ロートは「赤い」という意味のドイツ語だが、そのようにいつも頬が赤かった。目がいきいきと輝いていた。表情がゆたかだった。とても美人なのに、自分ではちっともそんなふうには思っていなかった。男っぽい、歯ぎれのいい話し方。いつも背すじをピンとのばして大股で歩いた。
われらの大切なミエさんが四十二歳で死んでしまった。ミュンヘンとウィーンで建築を勉強した。帰国後、一つ、二つと指を折るようにして少しずつ実績をつみあげ、やっと念願のロート美恵建築設計事務所を開いた。注文が舞い込みはじめた。その矢先のことだ。
朝起きると一枚のファックスが突然の死を知らせていた。
「……私たちは、だれも彼女の病を知らされていませんでした」
検査でガンが見つかったことは聞いていた。当人がまるで冗談ごとのようにひとこといった。しかし、そのあとすぐ仕事の話になって、いつものロート美恵にもどっていた。
「人に気をつかわせたくない。心配をかけたくないという心づかいを、最後までつらぬかれたようです」
三ヵ月ばかり前、たのまれていたものを送ったところ、ほんのちょっとしたことなのにお礼をしたいと言った。なじみのソバ屋にすわりこんで、三時間ちかくもいた。ミエさんは仕上げたばかりの住宅の写真をファィルにしており、それをひらきながら、少し得意そうに、いかにも楽しそうに話していた。
建築家は苦労のいる仕事なのだ。予算を決められている。そのなかで施主の注文を実現しなくてはならない。土地や法律の制約がある。建築現場は男世界であって、女ひとりは押しがきかない。大工は頑固者が多いのだ。施主が気まぐれをおこして、途中から新しい注文をつけてくるとどうなるか。
手まね、口まねが入って笑いころげた。断髪がりりしかった。目が星のように光っていた。赤い頬がなおのこと赤かった。
「じゃあ、これでお別れ——」
通りで振り返り、元気よくそう言った。それから背すじをピンとのぱして駅に消えた。うかつな私は、彼女がこの世の別れを告げにきたのに気づかなかった。
「残された私たちはせめて “楽しいひとときを一緒に過ごさせてくれてありがとう” と美恵さんに伝える小さな会を開きたいと思います……」
テーブルに軽いおつまみとビールにワイン。窓ぎわに写真やスライドが学芸会のように配置してあった。勉強家のミエさんは二冊の著書と、数冊の共著と、それに論文を建築雑誌に発表していた。それがまっ白な台の上に並べてあった。
彼女は、十年あまりヨーロッパにいた。ミエは、いまも旅に出ている。家族にも仲間たちにも、そんなふうに思わせてこの世から旅立った。なんというみごとな身の処し方だろう。
いまやミエさんは私の師匠になった。あざやかな手本をもらった。これからは何かあるとミエ師匠に相談しよう。ひそかに対話をして、歯切れのいい返事をもらう。そうやって自分のミットモなさを修正しよう。
設計事務所は空け渡さなくてはならない。主のいない部屋が一日だけ華やいだ。外に出て二階の窓を見上げてから私は靴のひもを締め直した。
「——これでお別れ」
おセンチになったりしたら、ミエさんがクスクス笑うだろう。私はいつも彼女がしたように背すじをのばすと、トットと駅に向かって歩きだした。
●文・絵=いけうち おさむ・ドイツ文学者