ウィーンお楽しみエッセイ
文:ロート美恵 イラスト:山口有史
1. 世界唯一の乗馬学校に魅せられて
1980年6月、初めてウィーンを訪れた。音楽の素養もない私が、まさかウィーンで生活することになるとは思いもよらない。しかし、この町には私をひどく虜にしたものがあった。
スペイン乗馬学校である。世界で唯一、ここでは、400年以上にもわたり古典馬場馬術が忠実に伝承されている。映画「うたかたの恋」の中で、スペイン乗馬学校が登場し、皇后工リザベートが乗馬を披露する優雅な場面が描かれていた。軍服姿の士官たちに混じり、紅一点、貴婦人独特の片乗りでワルツを踊るようなギャロップを見せる様子には、誠に古風なデカダンスが香る。
しかし、このような一見華やかな光景の裏で、かたくなに伝統を守る騎手と馬たちは、ハプスブルグ帝国が崩壊して久しい今もなお、何ごともなかったかのように日夜修行に励んでいる。厳しい管理の下、素質ある馬だけが次の世代に受け継がれていくという掟が踏襲されている。
────*─*─*─*─*────
スペイン乗馬学校で訓練を受けているのは、ユーゴスラビアのリピツァーナという馬で、彼らは毎年夏になると、故郷ユーゴとの国境近い牧場へ休養に出かける。芦毛の母馬に寄り添う子馬は黒炭のような青毛で、とても親子には見えずちぐはぐだが、彼らはやがて成長とともにグレーから純白、そして芦毛へと姿を変えていく。
さて、日頃訓棟を積んだ馬たちの晴れ舞台は、どのようなものだろうか。
入場の敬礼を終えた白い馬たちが、横一列に繰り出し、軽やかな音楽に合わせて、複雑なステップを踏みながら、対角線上を二手に分かれていく。二つのグループが、鏡に映し出されているかのように一糸乱れぬ同じ動きを繰り広げる様は、まさに神聖な白馬の舞いだ。そして、演技はさらに高度な技術を必要とする。停止位置のままスキップをするような「ピアッフェ」、上体を起こし、前肢を宙にかきながら後肢で力いっぱいに飛ぴ上がる「クーベット」等々、妙技は続く。
────*─*─*─*─*────
しかし、何といっても頂点は「カプリオーレ」だろう。これこそが、リピツァーナ馬の血統と厳しい訓棟の成果を試す技といえる。
「カプリオーレ」を前に馬体は緊張し、張りつめられた弓のような状態だ。騎手の側も後方に伏せたまま、ぴくりともしない。停止姿勢の馬の後肢に全体重がかけられ、バネのような威力で全身が宙に舞う。と同時に、後肢は思いきり後ろに蹴り上げられる。このとき、馬体は地上ほぼ2メートルの高さで、前肢も後肢もまったくの水平線上に浮かび上がる。
躍動する芸術の完成するこの瞬間が、時にとても長い時間のように思えるからふしぎだ。瞬きをするようなこの一瞬、騎手にも馬にも失敗は許されない。人馬一体になるというのは、このような状態を指すのであろうと、つくづく感銘してしまう。
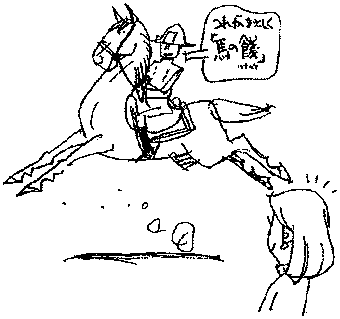
────*─*─*─*─*────
ウィーンと聞くと、誰もがまず連想するのは、音楽、あるいは生クリームのかかったザッハートルテだろう。けれど、このスペイン乗馬学校は、ウィーンの隠れた魅力のひとつだ。特に馬術家でなくても動物好きの人にとっては、練習風景だけでも一見の価値がある。
<終>
2. ハプスブルグ風休暇の過ごし方
オーストリアでは、年間25日以上の有給休暇があり、実際に利用することが義務づけられている。これにクリスマスや復活祭などを加えると、1ケ月はゆうに超える休日となり、日本人にとっては、夢のような話だ。
では、ウィーン子はどこでどのような休暇を過ごしているのだろうか。かつてハプスブルグ家が愛したという、とびきり優雅な保養地を紹介しよう。
────*─*─*─*─*────
山々の間に湖の点在する、ザルツブルグの南東一帯は、ザルツ・カマー・グート(塩の宝庫の意)と呼ばれ、ウィーン人の夏の保養地として、古くから親しまれている。映画「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台といえば、どんな所か想像できるだろう。なかでも、とくに “真珠” とうたわれるのがバート・イッシュルの町だ。
1823年、塩水を利用した湯治治療の成功をきっかけに、この町の保養地としての歴史が始まる。大転機となるのは、1828年、フランツ・カール大公と夫人ゾフィの訪問である。世継ぎに恵まれない大公夫妻にとって、湯治は政治的な責務とさえ言えた。そして、治療の効果であろうか、2年後の1830年、ハプスブルグ家の実質的な最後の皇帝となるフランツ・ヨゼフ1世が誕生する。夫妻の喜びはひとしおで、息子を “塩のプリンス” と呼んだほどだ。
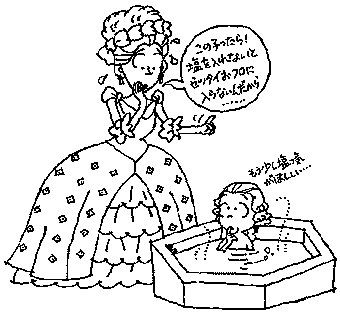
────*─*─*─*─*────
バート・イッシュルには、以来多くの人々が湯治に訪れ、現在、湯治施設には、男女20ずつの浴槽に加えて、サロンまで完備されている。ただ鉱泉につかるだけではなく、回廊に設置された飲泉場で、生温かい鉱泉を少しずつ飲みながら、ゆっくり散策をするのも治療プログラムのひとつだ。
さて、ヨーゼフが誕生してからというもの、大公一家はもとより、政治家や各国の王侯貴族が “皇帝のおそばで” と、この町に長期滞在するようになる。こうして、バート・イッシュルの夏は、ウイーンの政財界がそのまま引っ越してきたかのようなにぎわいを見せた。町のプロムナードは、優雅な貴族たちであふれ、おしやれなカフェも店開きをした。劇場では、フランツ・レーハーのオペレッタが連日上演された。
皇帝フランツ・ヨゼフが、まだ少女だったバイエルンのプリンセス、エリザベートを見初めたのもこの町でのことだった。
────*─*─*─*─*────
オーストリアに長らく住んでいたが、私の知る限り、この町ほどハプスブルグ王室の名残をとどめている所はない。
土産物を売るキヨスクでは、皇帝の時代の新聞が、デザインや書体は当時のまま、日付だけ現在に合わせて売られている。町を散歩する初老のカップルがまとう民族衣装さえもが、王室特有の洗練さや上品さを感じさせるのは、気のせいだろうか。
そして、バート・イッシュルでは、毎年8月18目、皇帝の誕生日に、亡き皇帝を偲び、町を挙げての祝典が催される。
今もなお、皇帝の再来をじっと待ち望んでいるかのように、訪れる者を不思議なタイムトリップへといざなうこの町で、ハプスブルグ風の休暇はいかがだろう。
<終>
3. ワインとグルメの季節
ウィーンから80キロほどドナウ川をさかのぼると、北岸の緩やかな傾斜地に見渡す限りのぶどう畑が広がっている。このあたり、バッハウ地方は、空の青さと透き通った空気を持つ大陸性の気候で、特に白ワインの産地として名高い。ぶどう畑とドナウ川を見下ろすように古城が佇み、川面に中世の町並みを写すこの地方の景色は、おとぎ話のようだ。
────*─*─*─*─*────
週末ともなれば、バッハウはボートや遊覧船で船遊びをする人々でにぎわう。でも、もちろん彼らの目当ては船遊びだけではないだろう。バッハウの秋はワインとグルメの季節だからだ。
ドナウ川を眺めながらの晩餐会は、こんな風に始まる。食前には「ホルンダーゼクト」で乾杯。ホルンダーという花の香りのするスパークリングワインだ。食事のワインを選んだら、前菜。秋といえば、かぼちゃのクリームスープはいかがだろう。ローストビーフとオニオンスライスにかぼちゃオイルとバルザミコ酢をかけた冷菜や、やぎのフレッシュチーズのサラダ仕立てもおすすめだ。やぎのチーズは臭みがなく、ヨーグルトのようでいてコクがある。
メインデイッシュはキノコ科理や栗をつめた鵞鳥の丸焼き。ゆっくりと時間をかけて楽しんだ晩餐会のとどめは、様々な野苺を使ったヨーグルトスフレ。もう、ダイエットなどあきらめるしかないでしょう。
────*─*─*─*─*────
さて、肝心のワインだが、ワインというとついフランスを連想するが、オーストリアの白ワインは絶品だ。「リースリング」はまろやかな口当たりで、本当にリースリングの花の香りがする。
「グリューナーフェルトリーナ」は、すっきりとした透明感が若々しい。さわやかな緑のイメージだ。オーストリアではワインを楽しむのは大人だけではなく、「モスト」と呼ばれるワインジュースは子供たちに人気がある。ワインの赤ちやん、「シュトルム」という発抱酒は口当たりもやさしい。20歳以上のお嬢様向けだが、ジュースのつもりで油断しようものなら大変、お腹の中で発泡を続けるため悪酔いの危険多し。
ところで、ワインを本当に楽しむためには、グラスにも注意が必要だ。大切なのは、ワインの香りと味を生かすグラスであること。液体がどのように口に流れるかで、本当に味が変わるのだから驚き。ワインを生かすも殺すも、グラス次第だ。
最近、オーストリアでは農薬、科学肥料を避け、自然栽培が注目されている。例えば、ハーブの効用。葡萄と一緒に畑にさまざまなハーブを植えると、ハーブの細やかな根が地中の微生物の活性化を促進し、葡萄によい影響を与えるという。
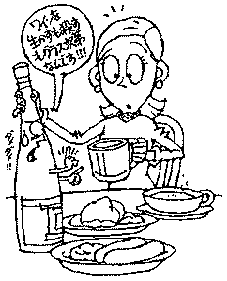
────*─*─*─*─*────
日本でも最近はオーストリアワインを置くレストランも見かけられるので、機会があれば、ぜひワインテイスティングに挑戦してみてはどうだろう。
来年夏には、岩手県大迫間町に「ベルンドルフ ブラッツ」* と銘打って、日本で初めて100種類ものオーストリアワインを揃えるワイン博物館が完成する。ワインテイスティングはもちろんのこと、オーストリア独自のイベントが計画されている。ワインのお好きな方はぜひ一度お出かけください。
<終>
(*現在「ヴィノテーク・オーストリア」という名でオープンしています。内装をロート美恵建築設計事務所が手がけています)
4. オーストリアのお祭り
2月上句から3月上句にかけてのオーストリアでは、「バル(舞踏会)」や「ファッシング(カーニヴァル)」と、さまざまな催しが目白押しだ。
フォーマルなバルに対して、冬を乗り越える国民的娯楽として生活に密着しているのがファッシング。とくに地方では、ファッシングのために時間をかけて手の込んだ衣装を作るなど、祭りへの深い意気込みを感じる。
────*─*─*─*─*────
なかでも有名なのが、東南部のシュタイアーマルク州で行われる「アウスゼー・カーニヴァル」。歌い手が「カーニヴァルの手紙」を吟唱する。諷刺画を手に、過ぎた年の馬鹿げた出来事をあざ笑うのだ。お婆さんが着るような寝巻きに仮面姿の吹奏楽団は、行進曲を吹き鳴らし、町中を行く。鬼のような格好の者たちが、頭に寵を載せ、箒を持って練り歩く。子供たちがふざけて彼らに雪玉をぶつけるが、これには「冬を追い出す」という願いが込められている。
一風変わっているのは、東部のブルゲンラント州で行われる「ブロッホ・ツィーエン」。これは、前の年に結婚式のなかった町でのみ行われる「疑似結婚式」の行列だ。ブロッホとは、枝を切り取り、飾り付けた木の幹のことで、またの名を「ヴァルト・ブラウト(森の嫁)」という。高いシルクハットをかぶった燕尾服の男性がブロッホに跨り、この奇妙な格好の「新郎・新婦」が町を行く。人々の笑い声で寒さも吹き飛ぶ、というわけだ。
────*─*─*─*─*────
一方、バルは、優雅なウィーンの伝統、とくに宮廷文化と深く結びついている。華やかな舞踏会場に足を踏み込むと、タイムマシンで時間をさかのぼってきたような錯覚に陥る。
オペラ座(国立歌劇場)で聞かれる最も華やかな舞踏会「オーパンバル」は、政治的にも社会的にもウィーン行事の最高峰とされている。ヨーロッパ各国の王侯貴族も顔を見せ、1990年にはモナコの王女カロリーヌがゲストとして来訪した。
オーパンバルの3ケ月前には、国内外から180組の男女が選別される。「デビュタント」といい、社交界にデビューする若き紳士・淑女たちだ。舞踏会当目、娘たちは純白の清楚なイヴニングドレス、若者たちは粋な燕尾服を身に纏い、まさにプリンスとプリンセスさながらの姿で登場する。国歌の演奏の後、彼らが何カ月も練習を積んだ「ポロネーゼ」を披露すると、夜明けまで続く大舞踏会の始まりだ。
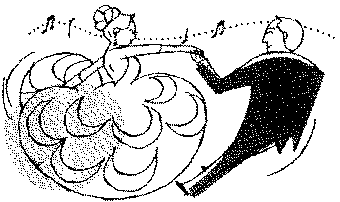
────*─*─*─*─*────
このオーパンバルに並んで有名なのが、楽友協会ホールで行われるウィーンフィル主催の「ヴィーナー・フィルハーモニカー・カーニヴァル」である。
しかし、このような豪華な舞踏会がすべてではない。気軽に楽しめる舞踏会も連日至る所で催されている。さまざまな職業団体が主催するものもあり、学生たちも学部に分かれて舞踏会を企画する。この季節、目抜き通りのショーウィンドウは、きらびやかなイヴニングドレスや燕尾服に占領される。
シンデレラのおとぎ話のような舞踏会も、仮装して別人になりすますカーニヴァルのタベも、長く厳しい冬を上手に過ごす人々の知恵なのかもしれない。
<終>
5. 都市生活の醍醐味を知るウィーンの街
ウィーンは都市に生活する醍醐味と豊かさがいたる所に点在している。今回はそんなスポットに焦点を当ててみよう。
1860年代、旧市街を囲む中世の城壁にとって替わって、リングシュトラーセ(環状道路)の整備が始まった。ハプスブルグ帝国の首都、ウィーンの威信をかけた大都市改造計画だ。それからわずか10年後、リングには豪奢な歴史懐古主義の建物が、次々と建設されていった。
オペラ座にブルグシアター。毎年元旦に行われるニューイヤーズコンサートで有名な楽友会館。少し時代はさかのぼるが、女帝マリア・テレジアの銅像を挟むように建つ美術史博物館と自然史博物館。ここは700年にもわたるハプスブルグ帝国時代に集められた絵画や鉱石をはじめ、気の遠くなるほどの収集品が眠っている。また、リングをはさんで反対側、国立図書館の一角、フィッシャー・フォン・エアラッハが親子二代にわたって設計した王宮図書館では、100年以上も前の書籍を手に取ることだって可能なのだ。
────*─*─*─*─*────
劇場やコンサートホールが祝祭の空間だとすれば、カフェはさながら町中に点在するリビングルームとでもいうところだろうか。ウィーンが誇る多くの文化も、このカフェから生まれていった。
ウィーン世紀末の若き芸術家たちはカフェで文学や芸術を語り合った。「カフェハーベルカ」の壁には、彼らがコーヒー代の代わりに置いていった絵が今もそのまま無造作にぶら下がっている。今ではどれも名画の誉れ高いものばかりだ。
カフェは店によって実にさまざまな顔をもっている。たいてい誰にでも行きつけのカフェがあるものだが、オペラ座裏の「チローラーホーフ」には、新聞を広げるネクタイ姿のビジネスマンの姿が目立つし、ルエーガー広場に面した「ブルッケル」には、ジャーナリストや若い芸術家たちの姿が目立つ。
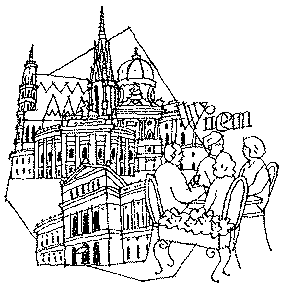
────*─*─*─*─*────
ブルッケルのサロンでは、いつもの顔ぶれが集まっていた。若い頃はさぞ美しかったに違いない銀色の髪をアップに結いあげた老婦人が、3人の男性を相手にブリッジに熱を入れている。その窓越しに見える、外のテラスでささやき合う恋人たちは、嬉しそうにいったい何を話しているのだろう。初夏は、もうすぐそこまで来ている。
<終>
6. ウィーン子は収集好き!?
ウィーンはマニアの町である。気ままな彼らは、昼を過ぎる頃からようやく活動を始め、獲物を求めて薄暗い路地を徘徊する。
オペラ座裏のアンナ通りで古書を取り扱う「ボーゲンシュタイン」はこだわりの出版社。今は亡き巨匠のオリジナル製図や建築に関する古書骨董の収集家は皆、ここに集まってくる。ウィーン子のお目当ては切手や版画、ブリキのゴーカートからマッチ箱にいたるまで、限りない。オーソドックスな骨董のデパートともいうべき「ドロテウム」では、人々がめぼしい品物にねらいを定め、オークションに望む。土曜日ともなると、マニアたちはその収集を誇りうらやみ、そして商談に時を忘れる。
数ある骨董商の中で特別な変わり種は、旧市街、シュピーゲル通りの「マックスヴェーバー医療骨董」だ。望遠鏡から顕微鏡、見るからに拷問具のようなメタリックの医療機器、果ては昔どこかの理科室にあったような人体解剖模型まで所狭しと並ぶ様には背筋が寒くなるほどだ。
────*─*─*─*─*────
類まれな、かつ風変わりなウィーン子の収集好きは、ハプスブルグ家に始まる。ハプスブルグの王侯貴族は、競い合い、憑かれたようにあらゆる収集に没頭していった。大公フェルディナンドの甥皇帝ルドルフ二世は、糞石の入手にはいかなる努力も借しまなかった。糞石(bezoar=解毒に由来するペルシャ語)とは、山羊、馬、ラマなど動物の内臓結石である。中世から近世にかけてこの糞石は、解毒剤として珍重されてきた。ルドルフ二世は、この石を心臓の上にのせることで憂鬱な精神状態から逃れられると信じていた。そして、苦労の未手に入れた貴重な石を、贅を尽くして飾り立てたのだった。
また、死亡率が極めて高く疫病や悪霊の恐怖に常にさらされていた王家の子供たちは、幼いときから、悪意ある視線から身を守る珊瑚など、様々な魔除けを身にまとうことが習わしだった。一族が偉大で権力を誇れば誇るほど、裏切りや、いかなる富とカをもってしても決して克服することのできない死への恐怖が、彼らを苛み、不安へと駆り立てたのかもしれない。
────*─*─*─*─*────
ウィーン美術史・自然史博物館、インスブルックのアンブラス城では、これらハプスブルグ一族の収集品を見ることができる。
歴代王侯の収集活動は、移り行く時代の流れとともに、より珍しい自然物、古代遺跡、高価な貨幣やカメオから芸術品に至るまで、その収集の対象を広げていった。
食物に混ぜられた毒を知らせるという蛇の舌は、実のところは鮫の歯の化石である。いくつもの蛇の舌(?)を金細工で包んだ、つぼみのような豪華な卓上飾り。これがご馳走と一緒に宮廷の食卓に並ぶとは、何と不気味なことだろう。房に束ねた動物の毛は、野牛のムスクなど動物の体臭や香辛料とともに、疫病を免れるために不可欠なオブジェであった。不格好な糞石と、それを飾る高価な貴金属や宝石との摩訶不思議なとりあわせ。グロテスクにさえ映るオブジェの数々が放つ、奇々怪々な魅力と危うさ。それは我々の知る機能や調和という法則を超えた驚異の世界だ。
ウィーンという町で、人々は知らぬ間に、極めつきのデカダンスの世界にはまってしまうのである。
<終>
